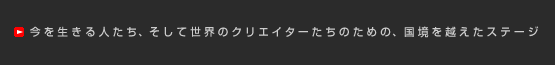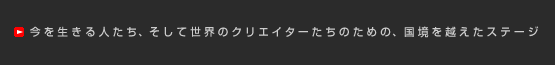ここ数年、ムーブメントらしきものが皆無である音楽シーンにおいて、唯一、それでもトレンドと呼べるのは、やはり“80'Sリバイバル”ということになるのだろうか。
けれど、この“80'S”が何を指すのかがあいまいだ。それはエレクトロニックなディスコの場合もあれば、ダークなニューウェーブの場合もあり、何かはっきりとした“音”の傾向というよりは、あくまでも気分のようなものが先行している感がある。
「“時代遅れ”なものが無くなった」とある人が言っていたが、この認識はあまりにも正しい。“80'Sリバイバル”の本質も“80'Sの復活”ではなくて、音楽シーンから“時代遅れ”なものが無くなったということなのではないだろうか。
これまで、流行はつねに先行する世代を“時代遅れ”にすることで、流行たりえてきた。そして、次の流行に押しやられてシーンから退場していった。
80年代でいえば、たとえばエレクトロニックなディスコサウンドは、当時コンピュータによるマシニックなサウンド自体が斬新であり、それゆえ最新モードとして存在していた。アナログという言葉がどこか哀れみをもって使われ、デジタルという言葉がもてはやされた。しかし、今では当時のコンピュータサウンドもすっかり古びたものに(ちょうど、初期スターウォーズのSFXが、CG全盛の今となってはどうしようもなくチープに見えるように)なってしまい、聴いていてもっとも恥ずかしいものになってしまった。
一方、ニューウェーブはそれこそ、それまでのロック/ポップスを完全否定することで生まれてきた。しかし、それゆえ音楽としての完成度には、疑問を持たざるを得ないもの多く、振り返って作品だけを取り上げれば、やはりある種の未熟さを感じさせ、同時代の感覚を持たないものには、あっという間にリアリティのないものとなってしまった。
それゆえ、ともに長らく封印されてきたわけだ。
しかし、パンドラの箱をチキン・リップスは開けた。
2002年にリリースされた彼らの2ndアルバム『Extended Play』は、80年代のエレクトロニックディスコが見事に再生され、“80'Sがキテる”という気分をシーンに定着させた。
そして、本作、チキン・リップスの3枚目のスタジオ・アルバムとなる『Making Faces』で展開される音。それは、薄っぺらなシンセと誇張されたギターリフ。わざとらしいファルセット、かと思えばときにデヴィッド・ボウイばりに見得を切るヴォーカル。そしてベースとドラムが演じるファンクネスはほとんど往年のディスコサウンドのパロディとしか思えない…。
しかし、これは奇をてらっただけのアナクロニズムではない。
単なる過去の焼き直しでも、ウラのウラを狙った一発芸でもない。時代の空気を皮膚で感取る者にしか掴むことができないある種の感覚を“音楽”としてカタチにすると必然的にこうなるのだ。この“音”はあらゆるものが並列して存在し、過去すべての時代のトレンドがアーカイビングされている“現在”を忠実に反映している。
よって、このアルバムを聴いて「エレクトロクラッシュなんてシャラ臭い! ディスコダブの方がクールだ!」などと口走ることだけは慎まなければならない。また、チキン・リップスのバイオグラフィーをあれやこれやと並べ立てたり、リリックを深読みするようなことも、どうしようもなく無意味なおこないだろう。彼らの音の背後に一体、何が存在しているというのだろうか? あるいは何かと比べる意味があるのだろうか? アンディ・ミッチャムもこう語っている。
「僕らがやっていることにメッセージを残すことは必要ない。80年代じゃないんだから」…。
けれど、その無意味なおこないを、あえてしてみることこそ、チキン・リップス的な振る舞いといえるかもしれない。
90年代初頭から、スタッフォードをベースに、アンディ・ミッチャムとディーン・メルディスは常にシーンのエッジを切り拓いてきた。2人はBizarre Inc.として、アシッド・ハウス/レイブ・カルチャーを新たなステージに引き上げた張本人なのである。
|